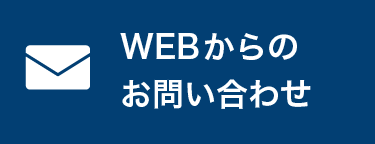コラム
医療法人の社員と理事
医療法人には社員という立場と、理事という立場があることはご存知かと思います。もっとも、社員と理事の違いについては、あまり、理解されていない方が多く、医療法人の社員や理事の方から御質問を受けることも少なくありません。そこで、本コラムでは、医療法人の社員と理事の違いについて、簡単に解説してみます。
はじめに
現在、医療法人の大部分は、出資持分有りの医療法人ですが、平成19年に施行された第五次医療法改正において、出資持ち分のある医療法人の新設ができなくなりましたので、今後、新設される医療法人は、出資持ち分のない医療法人となります。この点については、別途、ご説明をしたいと思いますが、本コラムでは、未だ、大多数を占める出資持ち分有りの医療法人を前提に話を進めます。
社員とは
社員とは、医療法人を構成するもので、株式会社の株主に相当するもので、社員総会を通じ、医療法人の重要な議決事項について意思決定をします。多くの社員は、株式会社の株主同様に、社員になるにあたり出資をしていますが、株式会社の株主とは違い、社員総会での議決権は、出資額の多寡に関わらず、1人1票です。
理事とは
社員総会で選出され社員総会から委任を受けて、医療法人の業務運営を行うもので、株式会社の取締役に当たります。通常は、理事会で協議をし、業務の運営を行いますが、代表権は、理事長だけが持ち、理事長が医療法人を代表します。
社員と理事の関係
上記の様に、あくまで、理事は社員総会により選任され、社員総会から委任を受けた範囲で業務運営を行うに過ぎません。株式会社では株主が重要事項の決定権限を持つように、医療法人では、社員たる地位が重要です。
多くの医療法人の定款では、理事は社員の中から選任すると規定されていますので、社員たる地位を失う時は、原則として理事も退任することになりますが、逆に、理事の地位を失ったとしても、社員の地位を失うということにはなりません。
以上、医療法人の社員と理事について簡単に説明をしましたが、個別のご相談等は、弊事務所までご遠慮なくご連絡ください。医療機関様のご相談については、医師兼弁護士の代表弁護士が、全国対応をしています。
交通事故被害者の方で、くびの痛みや違和感、上肢の痺れや疼痛などの症状が出現し、頸椎捻挫(いわゆるむち打ち症)と診断される方はかなり多くいらっしゃいますが、こういう交通事故被害者の方が、症状固定になった場合に、後遺障害等級認定では、どのような等級が認定されるでしょうか。
交通事故から半年から1年くらい経過し、症状が残存している場合には、症状固定ということで、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼し、後遺障害の等級認定の手続に進むが多いです。通常は、頸椎捻挫で認定される後遺障害等級は、12級13号、14級9号か非該当ですが、12級13号が認定されることは少ないです。
では、後遺障害等級認定で、12級13号、14級9号、非該当の認定は、どのような基準でなされるのでしょうか。後遺障害等級認定においては、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされていますが、実務上は、明らかな神経症状が残っていて、MRIなどの画像検査等の他覚的な所見が認められるものが12級13号、他覚的所見に乏しいものが14級9号、神経症状の残存が客観的に明らかといえないものが非該当といったように判断されているようです。大阪A&M法律事務所では、後遺障害等級認定や異議申立など交通事故のご相談をお受けしておりますので、ご相談ください。
皆さんの病院・医療法人は、顧問弁護士と契約をされていますでしょうか。顧問弁護士と契約されている病院・医療法人の皆さんは、顧問弁護士にどういった業務を依頼していますでしょうか。私が聞いている話では、もちろん、病院・医療法人の法律問題に詳しい顧問弁護士に依頼されている病院・医療法人も少なくないですが、院長先生の旧知の関係などから、地元の名士といわれるような弁護士と契約されている病院・医療法人も多くあり、あまり顧問弁護士を活用できていない病院も少なくないようです。また、そもそも、顧問弁護士と契約していない病院・医療法人や診療所の方が、多いようです。
しかしながら、病院・医療法人や診療所がかかえる法的問題は、日常生じる取引先との契約や、従業員との労務関係だけでなく、医療事故(医療過誤)・個人情報の流出といった突然訪れる重大なものや、日々の診療の中で生じる患者・家族からのクレーム対応(モンスターペイシェント)などもあります。特に医療事故やクレーム対応などについては、迅速かつ適切な初期対応が重要です。このような医療機関の抱える法的問題に迅速括適切に対応するためには、病院・医療法人の法律問題に精通した顧問弁護士と日常から連携し、予防処置を講じると共に、問題発生時には、弁護士とすぐに連絡を取れる体制をとっておくことが重要です。当事務所の代表弁護士は、現役の医師である上に、大学病院の医療安全にも関与しており、病院や診療所のあらゆる法律問題に対応が可能ですし、日常から、院内での医療安全講習のお手伝いなどもさせて頂いております。
また、多くの病院・医療法人において、診療報酬の未収金は悩みの種かと思います。未収金問題は、やはり、発生させないようにすることが重要です.当事務所では、顧問弁護士として、未収金の発生予防の相談にも応じられますし、未収金回収の代行業務もさせて頂いております。
当事務所と顧問契約をさせて頂く際の費用の目安はこちらですが、医療機関の規模や業得内容等により、相談に応じさせて頂きます。また、医療機関の顧問契約については全国対応いたします。
初回の相談は、無料相談(交通費実費で出張相談も可能です。)とさせて頂きますので、まずはご遠慮なくご連絡ください。